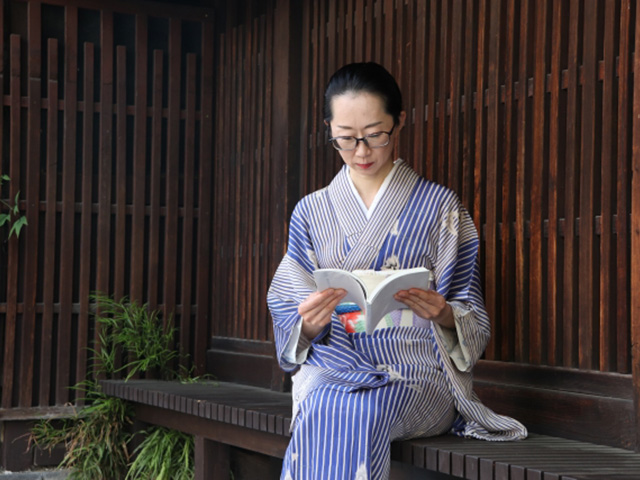『着物憑き』、というと、着物にまつわるホラーかと思われますが、こちらは着物に関するエッセイです。
加門七海先生ご自身の着物体験や歴史や民俗学視点の着物知識がとても興味深く、勉強になります。
「しつけ糸を夜に解いてはいけない」なんて、この本を読むまで知りませんでした。
自然と学べる着物の知識
加門七海さんの本では、糸や織りの種類、その歴史的背景や呪い・縁起物としての「着物」という文化を総合的に学ぶことができます。
東と西
日本の東西では着物の着付け、帯の結び方、草履の履き方、色や柄まで、はっきりと違いがありました。
しかし、今ではほとんど差異はなくなってきたそうです。ただ、色や柄の好みだけは関東、関西で今も異なるそうです。
そんな東と西の着物の違いを、東京の鏑木清方と京都の上村松園の絵で比較しています。粋な鏑木清方と凛とした上村松園、着物に注目して絵を眺めるとその差異が際立ちます。
昔と今
着物が日常着だった昔と、非日常着となった現代では、作り方も着方も違なります。着心地を重視した糸や織り方が追求され、着物を「育てる」文化があったそうです。
加門七海さんご自身も「育てる」ために堅い紬をわざと寝間着などに使っていたそう。
昔の着物は使い捨てる服ではなく、何代にも渡って寄り添う相棒のような存在だったのでしょう。
着付けも、昔は浮世絵のようにゆったりと体に沿っていたのに、フォーマルを基準にしたきっちりした着付けに変わってしまいました。
それが、「着物警察」や悪徳着付け教室の台頭を許し、着物は窮屈なものになってしまったのです。
現代の着物は、体を縛り付ける悪しき布になってしまったわけだ。
『着物憑き』本文よりー
着物にまつわる不思議な話
私はよく骨董市などで安い着物を購入しますが、心配なのは着物にまつわる「念」です。
そうした着物は、できる限りクリーニングに出し、日に当ててすぐには着ないようにしています。
念を断つ
昔の着物は反物から仕立ててその人の寸法・体型に合わせてつくられるオーダーメイド。人形などと同じく、作られた人、着る人の「形代」でもあるのですから。
加門七海さんは「見える人」ですので、着物の怪にも出会うことがあるそうです。それを避けるために行うのが「糸を変える」こと。
古い着物は洗い張りや寸法直しで、つくられた思いや念を「解く」ことになるのだとか。
着物は縁起物であり、呪物でもある
日本の着物の文様は、その殆どが縁起物・厄除けの意味を持ちます。実は骸骨なども厄除けの意味があるとか。
昔から日本人は文様に願いを込めてきたので、呪具としてのアクセサリーは必要なかったという解釈は「なるほど」なと思いました。
アンティーク着物は魅力ですが、きちんと礼を尽くすというのが大事なのだなと。
また、なにか違和感があるときは手をださないのが懸命です。特に「自分の『個性』が理由もなくぶれたときは気をつけろ」とのことです。そうした場合、自分の意志ではない何かが潜んでいることも…。
着物憑きとは
本作は着物にまつわる心霊体験も書かれていますが、一番恐ろしいのは人の執着かもしれません。
この本を読んで感じたのは、着物にまつわる恐ろしさと、それを上回る素晴らしさです。
怖い話もでてきますが、それらは、きちんと着物と向き合うための教訓にも思えました。
着物憑きとは結局、着物に対する執着ではなく愛なのではないかと。
猛暑の中、苦労して夏着物を着る加門七海さんはこうおっしゃっています。
なぜ、そんな苦労までして着物を着るのかかといえば、着たいという気持ち以外に理由はない
『着物憑き』本文よりー
私の着物は着付けも管理も適当です。なので、これからはもう少し、着物と向き合えるようになりたいです。