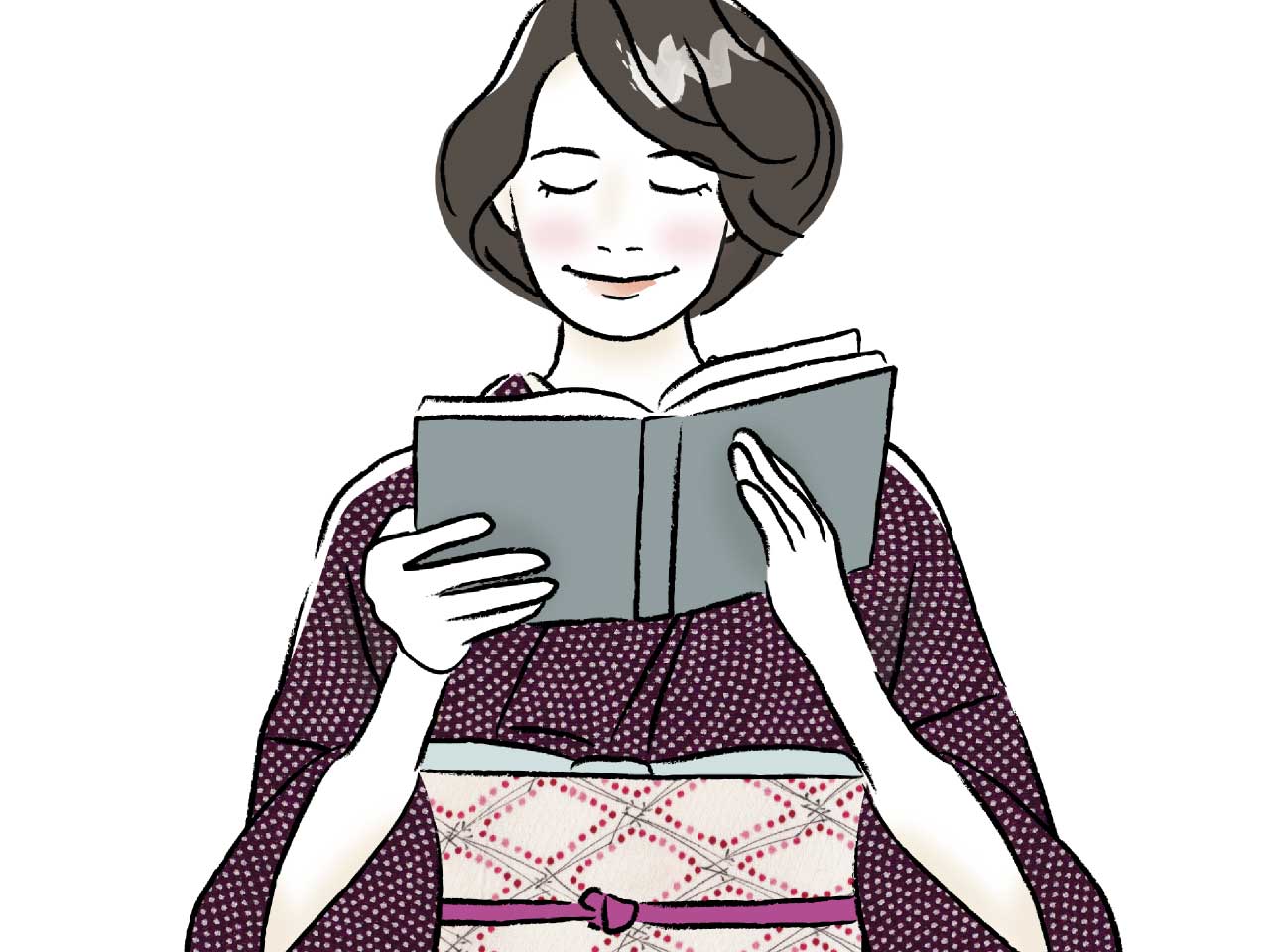着物と防災について、私が感じたこと。それは「着物で地震にあったらとても不便」だということです。
着物はどうしても、洋服よりも動きづらいのが難点です。特に草履や下駄は、よほど慣れていないと走ることもできないし、袖をひっかけて転ぶ可能性だってある。
でも、着物でお出かけはしたい…。そこで、私なりに考えた着物での防災について書きました。
足元の防災
着物で地震や災害にあった場合、いちばん困るのが足元だと思います。草履や下駄では走れないし、地震でボコボコになった道を歩くだけでも大変です。
草履や下駄に慣れていないと、転ぶ心配だってあります。
時代劇でも、逃げる時に草履を脱いで懐にしまって裸足で走り出すというシーンをよくみかけますから。
じゃあ、どうするかというと…
「ぺたこさん」こと石橋富士子さんが、『知識ゼロからの着物と遊ぶ』という本の中で、着物で東日本大震災にあわれたときの様子を伝えてくれています。
ぺたこさんが着物で被災された時、まず、たすき掛けをしました。その後、スニーカーのような歩ける靴を購入して履き替え、なんとか帰宅されたそうです。
この本を読んでから、私は防災用に足袋シューズを買いました。着物でちょっと遠出するときや、土地勘のない場所へ行くときは、軽めの足袋シューズと靴下をバッグにいれておきます。

こうした携帯用の足袋スニーカーと靴下は、草履で歩き疲れた時、履き替えることもできます。荷物は重くなりますが…。
最近では、軽くて持ち運びしやすい足袋スニーカーも種類が増えました。いざというときに一つ、もっておくと便利です。
着物と帯を動きやすくする
着物で災害にあったときの難点は、「袖」と「帯」だと思います。
構造上、着物の袖は、洋服の袖とは違って幅が広くなっています。そのため、災害時に引っ掛けやすい。走ると帯も崩れそうですよね。
紐でお太鼓結びを固定
そこで、帯の固定については、歴史ドラマを参考にしています。以前の大河ドラマ『八重の桜』で、明治時代の女性が炊事の時にお太鼓の帯を紐で固定していました。
お太鼓結びの帯にも一本、紐を回して固定しておくのもいいかな、と思います。かわいい柄物の腰紐だったら気分もあがりますしね。
たすき掛け
袖はたすき掛けをします。これなら少し動きやすくなりますので、バッグの中に紐を何本かいれておくと安心です。
簡単なたすき掛けの方法はこちら
裾は尻ぱしょり
着物の裾は、裾をめくり上げて帯に挟む「尻ぱしょり」にすれば、走りやすくなりそうです。しかしこれは、着物警察あたりに「はしたない」と言われそうですが…。
でも、災害時はそんなことも言ってられませんしね。
まとめ
着物の着付けやファッション情報は多いのに「災害時の着物」について触れている人はほとんどいません。
着物初心者の私が考えた「着物と防災」なんて、たかが知れているのです。
できれば雑誌『七緒』やきくちいまさん、大久保信子先生などの専門家に「着物と防災について」の本を書いてほしい。
いざという時、着物での対処の仕方がわかっていれば、安心して出かけられると思うので…。